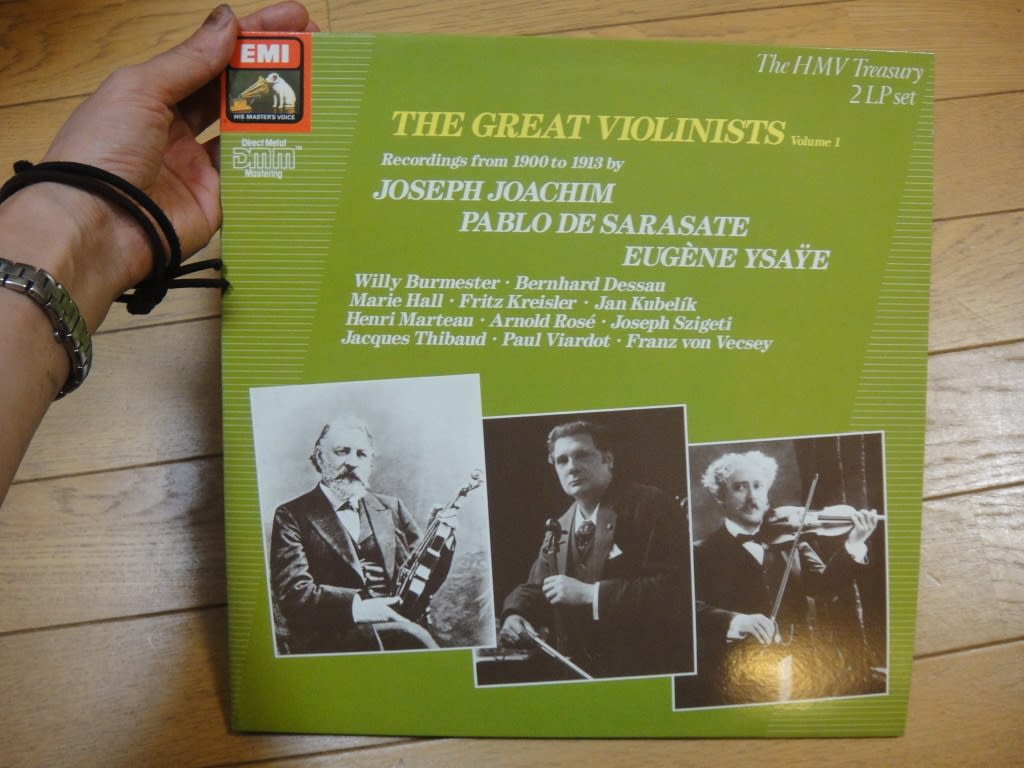7月初旬、ジャガイモの収穫がようやく終わりました。
数日おきにしっかり雨が降るため畑はすっかり田んぼ化しており、泥の中から発掘するような、かなりキビシイ作業でした。
いつもならば、ほろっとほぐれる土の中から「こんころり〜ん」とお芋が転がり出てきて、「わ〜い☆」となるのですが、今年はそうは行きません。
べちょべちょの土にスコップを突き刺し、重たい先端を何とか持ち上げます。
ぐっちゃりした泥を別の所に積み上げ、発掘作業のように、掘り上げた泥、そして穴のなかからジャガイモを探し出す、という感じ。
ニンニクの時も大変だと思いましたが、あれは、1本の茎をつかめば、その下にある1個のニンニクを掘り出すことが出来ました。
ジャガイモの場合は、茎が生きていたとしても地下茎から外れてしまっている芋も多く、更には地上部がすっかり枯れているものも多数。泥の中に埋まり込んだ芋を捜すのは、かなり大変・・・・・。
そして掘り上げてみると、収穫量は、だいぶ少ないです。おそらく次のような理由ではないかと・・。
・びちょびちょと田んぼのように地下水位が高かったため、病気で腐った芋が例年よりも多いはず。
・泥まみれのため、掘る際にみつけられなかった芋がおそらくだいぶある。
・ネズミ被害芋は、ぱっと見はあまり目立たなかったが、ネズミにかじられた芋は、濡れた土の中で腐ってしまって分からなくなった可能性がある。(泥んこの畑なのに地下のネズミ通路は浸水していないのだろうか)
・あと、全体的に肥料が足りなかったかもしれない。
数回に分けて掘ったので、各品種の全収穫量が分かる写真はあまりないのですが、スナップをいくつか・・。
![2014/06/18キタアカリ収穫 ジャガイモ収穫]()
キタアカリ。これは収穫の一部。
紫色のお芋は、昨年収穫したジャガキッズパープル(多分)の余りを埋めておいたもの。
![2014/06/26紫月収穫 ジャガイモ収穫]()
こちらは紫月。
つるりと丸く、薄めの紫色。
皮の色は茹でると色落ちし、中がグレーに染まります。
![2014/06/26紫月収穫 ジャガイモ収穫]()
右側が紫月なのですが、これで全収穫。
500g植えて1.2kgの収穫でした。
左はサッシー(多分。よく分からなくなってしまった)。
![2014/06/18インカルビー収穫 ジャガイモ収穫]()
左がジョアンナ。極少の芋を植えたら、採れた芋も極少・・・。
右はインカルージュ。
皮は厚めで、綺麗な赤色。茹でても色落ちせず、中に皮の色は染まりません。インカのめざめの、赤皮に変異した品種のようです。
ほくほく・むっちりの濃い黄色のお芋で、美味しいです。これはまた育てたいかも。
(極早生なので芽が出やすいので要注意)
![2014/07/03ディンキー収穫 ジャガイモ収穫]()
ディンキー。
皮の色はカタログ写真ではもっと濃い赤だったがこれは薄いピンク。
地下茎から外れ、土中で水に浸かった状態で色が薄れたのかもしれない(サツマイモでもそういうことがある)。
すべっとなめらかな、皮が剥きやすい形状です。
![2014/07/03ディンキー収穫 ジャガイモ収穫]()
7月に入ってから収穫したのですが、こんなイボイボのものが。
二次成長ってやつでしたっけ?
![2014/タワラマゼラン収穫 ジャガイモ収穫]()
タワラマゼラン。
今回、一番地上部の成長がよくぶっとい茎になっていました。収穫量もよかったです。
芋は大きいものも結構とれ、それぞれ比重がずっしり重ため。
色が黒くて見えにくいからか、皮が固いのか、ネズミやキジの被害が少なかったような気がします。
これは又育ててもいいかも。
丸/小判型
品種名
(文字色は外皮の色)
特徴
種芋重量(個数・植え付け箇所)
収穫
味など
まる
キタアカリ
ジャガイモシストセンチュウに抵抗性。 ビタミンCが多く、食味も優れる。 早生、多収である。
植え付け:1kg(16個・16箇所)
収穫:4.6kg(4.6kg/kg、0.28kg/箇所)
美味しいので我が家のスタンダード。ただ、一番ネズミに狙われやすい気がする。
紫月
いもの断面が満月みたいに美しいのが名の由来。
中心空洞や褐色心腐などの生理障害がほとんどなく、育てやすい品種。
「男爵薯」と同じくらい食味に優れている。
中早生。紫皮。肉は淡黄肉。やや粘質。
植え付け:0.5kg(7個・7箇所)
収穫:1.2kg(2.4kg/kg、0.17/箇所)
皮ごと茹でると中に色が染まる。
味は普通かな・・。
サッシー
ホクホク旨い黄肉品種。
中玉イモがごろごろ採れる豊産性で、疫病にも強い。
油と相性が良く、フライやポテトチップスに向く。
晩生。黄皮。黄肉。粉質
塊茎数が多く小玉になりやすいので、茎数は2〜3本とし株間を広げる。
最初の芽が折れると、次の芽が出づらいので、最初の芽を折らないように注意。
植え付け:0.5kg(5個・6箇所)
収穫:0.8kg(1.6kg/kg、0.13/箇所)
収穫後、キタアカリと混ざってしまって味見はまだです。
インカルージュ
ナッツのような独特の香ばしさとさつまいものような甘味は、やみつきになる旨さ。
煮崩れも少ない。皮の部分にはアントシアニンを含み、カロテノイドを「インカのめざめ」よりも多く含んでいる。
極早生。赤皮。橙肉。粘度は中。
植え付け:0.5kg(12個・12箇所)
収穫:2.8kg(5.6kg/kg、0.23kg/箇所)
茹でると、皮の下にデンプンが沢山あるせいか、するっと皮が剥ける。皮の色は肉には移らない。
肉質もホクホク。
美味しいのでまた育てたい。
小判型
ジョアンナ
美食の国・フランスで非常に高い評価を得ている品種。
香りが大変良く、甘味たっぷりの黄肉は最高の旨さ。
豊かな風味を生かした、じゃがいもが主役にお料理に最適。
収量も多く豊産性。
中晩生。黄皮。黄肉。粘質。
いもが長形なので、十分な覆土を行い、緑化いもが発生しないように注意。
植え付け:0.5kg
(20個・20箇所) 極少の種芋
収穫:3.2kg(6.4kg/kg、0.16kg/箇所)
地上部が6月中旬に枯れてしまったものは、極小のクズイモのみ。
7月まで生き残っていたものは、まあまあの大きさに。
味は、クズイモの場合は水っぽいが、ちゃんとした大きさの芋ならばまあまあ。 「最高の旨さ」かなあ?
ディンキー
長円形でホクホクとした食感で食味よい品種。
赤皮が美しく、芽も浅いので皮ごと料理に使っても綺麗。
たっぷりとれる豊産性。
中晩生。淡赤皮。身の色は白肉。やや粉質。
やや粉状そうか病が発生しやすいので、排水の良い圃場を選んで植付ける。
植え付け:0.5kg(9個・9箇所)
収穫:3.2kg(6.4kg/kg、0.35kg/箇所)
薄いピンクの皮。
味はまあまあ。
タワラマゼラン
濃い紫皮のおかげで緑化せず、イヤなエグミが発生しない。
食感はホクホクなのに舌触りは滑らか。
甘味と香ばしさがたっぷりで、食べ味極上。
煮崩れしにくいのであらゆる料理に使える。
病気に強く、収量も多い優秀ジャガイモ。
中生。紫皮。黄肉。やや粉質。
植え付け:0.5kg(4個・7箇所)
収穫:5.6kg(11.2kg/kg、0.8kg/箇所)
地上部は7月初旬になっても元気で、地下茎もしっかり芋につながっていた。もっとおいておいてもよかったのかも?
皮を剥くと白っぽいが、茹でると黄色みが強くなる。割とおいしい。
ジャガキッズパープルと似ているかも?
まだ個別にちゃんと味見していませんが、又植えたいのは、インカルージュ、タワラマゼランの2つ。
芋の比重がずっしりした感じでデンプンがのって味がいいような気がします。
紫月は、皮の色が中に移るので、いまひとつ。
ジョアンナ、ディンキーは、もしサイズが大きいのがとれれば、皮が剥きやすいつるりとした形状なのはいいです。
でも今回は大きい芋はあまりなし・・。
特にジョアンナは、種芋が小さかったからか、芋のサイズが小さすぎでした。
大きい種芋なら大きいのがとれるのかなあ。
味はこれから再度チェック。