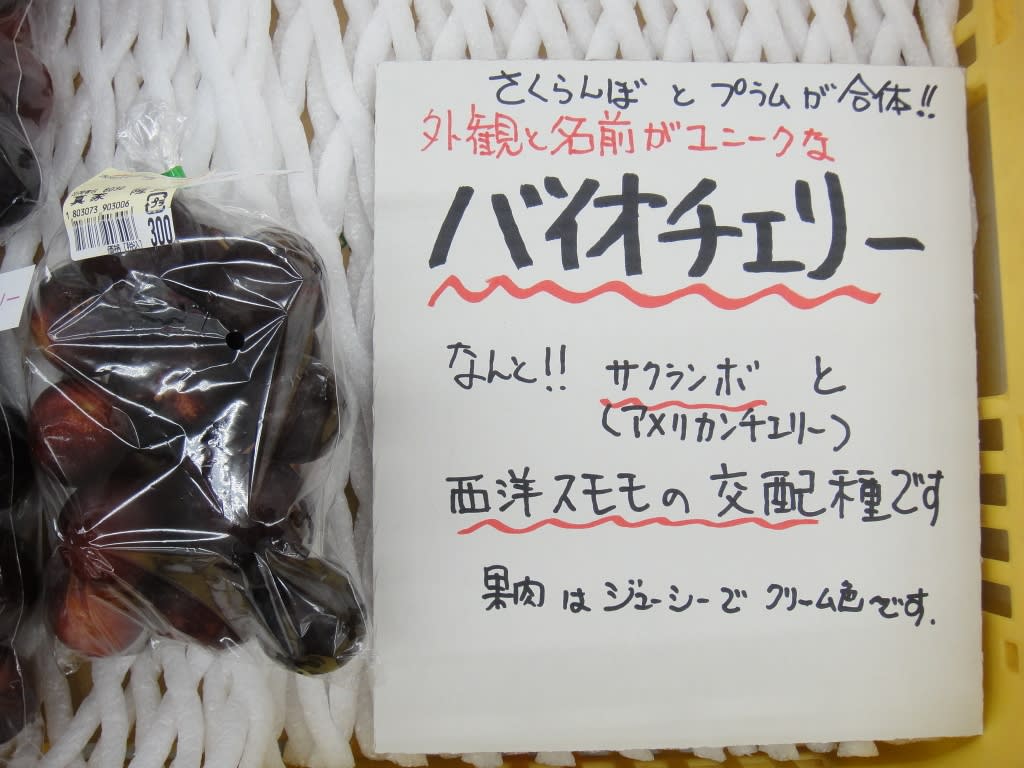2014年4月に行ったウィーン旅行の記録です。
===
ナッシュマルクトはおそらくウィーンで一番有名な路上マーケットです。
余りに人気なので、観光客ずれしているだとか、値段が高い、という評価もありますが、やはりお金を使う人達(観光客)が集まるだけあって、品揃えが非常に豊富で、ヨーロッパや中近東一帯からいいものを集めてきている、という感じ。
殊に最近は、数年前よりも移民が多くなっているのか、多国籍度合いが増しているように思います。
(オーストリアのものだけに限定したらきっと寂しいマーケットになってしまうはず)
そしてどのお店も、ディスプレイにも気を遣っています。一目見て、わー素敵!と思ってしまいます。
日本で言うと高級スーパーの紀伊国屋みたいなものかな?
買うかどうかは別ですが、やはり行く価値はあるマーケットだと思います。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
こちらはイタリア風お総菜店。
チェリーペッパーにチーズを詰めたものや、イカにエビを摘めたもの、アーティチョークの詰め物、寄せタコの薄切りなどなど。
写真一番手前は、エビ風かまぼこかも。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
様々なフェタチーズ 、モッツァレラチーズ。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
Wandererschnitteというもの。数年間は見なかった気がします。数軒のお店にあったので流行っているのかな?
これは各種ドライフルーツやナッツを練り固めた、エナジーバー、又はペミカン(?)みたいなもののようです。
材料は、レーズン、デーツ、スモモzwetschken(ドライプルーンかな?)、クランベリー、サワーチェリー、アプリコット、ピーナツ,、ヘーゼルナッツ、ブラジルナッツ、パンプキンシード、フラックスシード(亜麻の実)、ひまわりの種、キャロブパウダー(キャロブの木のことはJohannisbrotbaum というのだとか)。
小麦粉、卵、油脂は不使用。
非加熱圧縮加工。 VEGAN食品。
あるお店で少しだけ味見しましたが、とても濃厚。
以前作ったプルーンログみたいな感じでした。
あんな感じで、栄養のありそうなものをどんどん混ぜていけば、似たようなものができそうです。
美味しいけれど、沢山食べたら太りそうな感じ。というか、沢山食べるものじゃないか。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
オリーブ各種。
奥はパンに塗るペーストなど。
こういうおつまみ屋さんは、グラス売りのワイン屋さんも併設していて、つまみ+ワインでちょっと一服出来るようになっていました。
でも(土曜だったので)非常に混雑しており、慣れないシステムで外国語で注文をこなすのは大変なので、この日は諦めました。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
スナック類を買い食い出来るお店も色々あります。
ケバブやボレッキはもはや定番(ターフェルシュピッツやカツレツなどのいわゆるオーストリア料理より私はこっちが好き)。
そして今回初めてみたのがロシア系のお店。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
いろいろな包みパンがありました。どれも大きいので買いそびれてしまった。次に行ったら何か買おう!
(朝食をたっぷり食べると、こういう買い食いをしにくいという問題点が・・)
土曜日は、常設店舗に加えて、ファーマーズマーケットの日。
ナッシュマルクトでも、南端側、そして市場の中程のところどころに、生産者直売店が出ていました。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
瓶詰め好きの心をくすぐる素敵なもの達。
百合(おそらく甘草?)のツボミのピクルスや、唐辛子のピクルス。
小瓶は唐辛子ペーストかなあ。 小瓶でいいから買えばよかったな・・・。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
こちらのお兄さんは、チーズ屋さん。
沢山説明して下さいました。
(シャッターを押すのが遅れてにっこり顔を逃してしまった)
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
工房特製の色々なチーズたち。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
山羊乳のチーズ。
(説明文を訳すほどはドイツ語出来ません。すみません)
美味しいので一玉買ってしまいました。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
葉っぱで包んで甘いワインに漬け込んだチーズ、だったかな・・・。
これも美味。
ワインと一緒に食べると幸せな味です。
他にも、お酒に漬けたチーズが何種類もありました。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
工房の様子のボードがあったので、写真を撮らせてもらいました。
![2014/04/26ナッシュマルクト naschmarkt]()
とても日に焼けたお兄さんの周りにあるのは、苺、リンゴ、ナシ、ニンニク、干し洋梨(詳しくは別記事で)。茶色い丸いものは胡桃(現場では胡桃に気づかなかった。気づいてたら買ったのに〜)