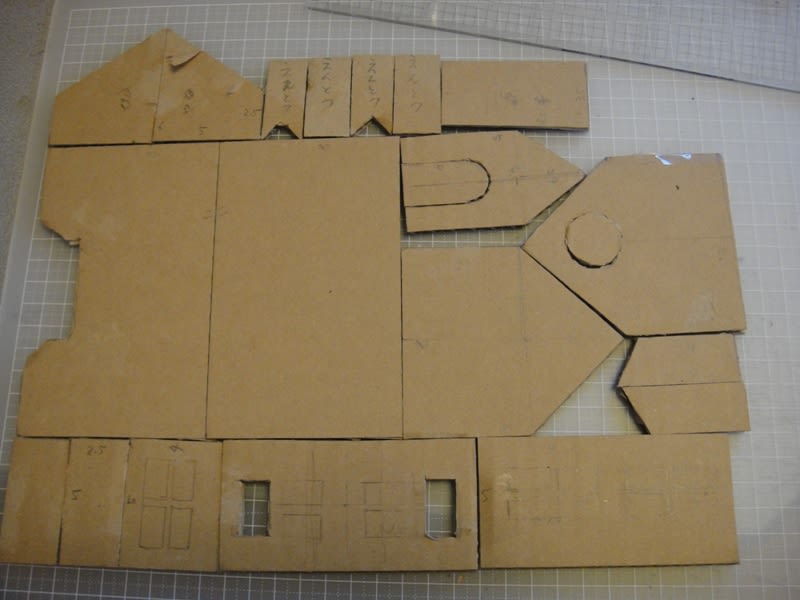2013年の年末も、スモークサーモンを沢山作りました。
大量生産は、昨年に続いて2回目。
去年よりは要領よく作業が進みました。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
今年のサーモンはノルウェー産で、1匹1.2キロ程度のもの。
昨年のチリ産よりだいぶ小さめです。
なので、今年は8匹(半身16枚)スモークしちゃいます!
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
大きめのトロ箱を母が貰ってきてくれました。
ソミュール液は前日に煮溶かしてあって、10リットル用意。
容器が大きいので10リットルでもこの程度・・・。
(昨年は5リットルで量が少ないという反省があった)
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
まな板の周りには紙を敷いておくと後が楽だそうです。
(年末には新聞紙を捨てずにとっておくべし)
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
ウロコとり。
鮭の皮はけっこう丈夫なので、ガシガシやっても大丈夫。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
三枚おろしは、今年は父と私も挑戦しました。
母が4枚。父2枚、Fujika2枚。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
漬け込んだ状態。
たっぷりめのソミュール液に、鮭が泳いでいる状態です。
(液10リットル、鮭9キロ)
この撮影時で15:47。
塩分濃度が均一になるように、夜寝る前にソミュール液をかきまぜ、鮭の上下も置き換えたりしてみました。
この後、ソミュール液を一部とりわけ、ハラスの部分を別の袋で漬け込みました。 (別袋にしたのは正解。ハラスは脂が多いため結構汚れる)
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
父や私が大名おろしでさばいたので、中骨には身が沢山。
塩ゆでしてほぐします。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
すごく沢山とれました。
これは、一部は冷凍。一部は母の好きなふりかけに。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
翌朝、サーモンをチェックしてみると、明らかに去年と違うさわり心地。
むちっと固く締まっています。
でも食べてみるとかなり塩辛いので、塩抜きをすることに。
一旦鮭を全部取り出し、ソミュール液を捨て、水を張ります。
ここに鮭を入れて、水をちょろちょろ出しながら、1時間弱(朝食の時間中くらい)。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
塩抜き後味見すると、しっぽの先端で、「あら、薄いかな」くらい。
これでよしとします。
もう少し砂糖を入れてもよかったかも、という母の意見で、ブランデーに三温糖を溶かして刷毛で塗ってみました。
先程のトロ箱を綺麗にして、ピチットでサンドイッチするように鮭を配置。しばらく脱水させます。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
ハラスは、塩抜きはせず、ゆすいだ後に吊して干します。
16枚分のハラス。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
24時間後、スモークし始めます。
スモークに向けて12枚がスタンバっています。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
網に置くと、スモーカー1台あたり6枚置けます。
2台で12枚。
ハラスもいくつか一緒にスモーク。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
残り4枚はとある本のホテルのレシピを参考に、太白胡麻油に漬けてみることにしました。
大きな袋に身を下にして置き、そこに太白胡麻油200ccを流し込みます。完全にはひたらないけれど、身の側が浸っていればいいかな、と・・・。
この後はあまり写真がないです。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
出来ちゃいました。
こちらは油漬けなしの方。
むっちりして生ハムみたいな感じで、なかなかいい感じに出来上がりました。
![2013/12/28自作スモークサーモン スモークサーモン]()
プレゼント用にはこんな感じで。
段ボールにアルミ箔をかぶせ台にします。
サーモンをのせてオーブンペーパーでくるんでしばって固定。
今年のサーモンは小さめだったので、半身プレゼントするのに丁度いい大きさだったように思います。
美味しいし、プレゼントした先では好評で、母も満足の様子。
■今後の課題
・来年は、塩分濃度11%、砂糖はその3分の1の3.6%でどうだろうか。
ソミュール液は10リットルで足りる感じ。
・オイル漬けすると身が痩せにくいような気がした。
味はほぼ同じか、やや塩味マイルドに感じるかもしれない。
スライスしたサーモンは、とてもテリテリした感じになる(ホテルでこうやるのが分かるような感じ)。
オイル漬けは必須ではない気がするが、万一塩味が濃すぎた場合には有効かも。
・そろそろ本格的に、木製のスモーカーを作るかな?
片付けやすいように組み立て式で出来るだろうか。
お父さんへ:設計してみませんか?
・真空パック機があるといいかも、との母の意見。今年中に買おうかと思っています。
おすすめ機種がありましたらアドバイスお願い致します。
■参考情報
木製などの自作スモーカー各種
みなさん本格的に作っているので、組み立て式のものはないようです。
■スモークサーモン 2013年のスケジュール
オイル漬けしなかったもの(12枚)
オイル漬けしたもの(4枚)
12/26
サーモン到着
寒い部屋におき、毛布にくるんで冷やしておく。
12/27
夜、ソミュール液作成(by母)
12/28
私は朝から実家に向けて移動。昼すぎに到着。
昼食後、解体開始。
大きな漬け物袋にソミュール液を入れ、出来たものから漬けていく。
16:00前頃、解体終了(所要時間約3時間)。
(最初と最後のでは漬け時間に随分差があるってことになるが・・・・)
ハラスは、ソミュール液を一部とりわけ、別の袋で漬けた。
解体終了後は、アラをゆでてほぐしたりなど。
夜、ソミュール液をかきまぜ、鮭の上下を置き換えたりしてみた。
12/29
(塩漬け約16時間)
朝起きてすぐ(8時前頃)、サーモンをチェック。
去年より随分固くしまっている様子。(昨年はぐにょん、としていた)
味見するとかなり塩辛いので塩抜きすることに決定。
ソミュール液を捨て、袋の中に新しい水を入れてシャワーの水をちょろちょろ出しながら塩抜き。
(塩抜き約1時間)
朝食後味見。シッポの先端で、あら、薄いかな、という程度。
よくゆすいでヌメリをとり、キッチンペーパーでふいてお盆に仮置き。
もう少し甘くてもいいかなと思ったので、ブランデーに三温糖を溶かして刷毛で塗ってみた。
トロ箱を一旦綺麗にし、ピチットシートでサンドするようにサーモンを配置。
12/30
(ピチット脱水約24時間)
朝からスモークする場所の準備およびスモーカーの作成(2台必要なのだが1台こわれていたため)。
昼前にピチットシートから外し、 網にのせてスモーク開始(スモーカー2台。各6枚で12枚分)。
夜は網にのせたまま室内にとりこみ。
スモークの段取りが終わった昼頃、4枚分を白胡麻油に漬けはじめ。
(オイル漬け約10時間)
夜寝る前、オイルから取り出し、ピチットシートに挟んでおく。
(ピチット一晩)
12/31
スモーク二日目。
棒からぶら下げる方法でスモーク。 こうするとスモーカー1台で12枚。
空いた方のスモーカーでスモーク1日目。
1/1
出来上がったものから包んで、母がお友達に配ってきた。
(この日はスモークしなかったような?)
塩漬け豚肉の塩抜き(by父)
1/2
新年会にて試食。
スモーク2日目。塩漬け豚肉も同時にスモーク。
〜1/14
3枚持ち帰って冷凍しなかった1枚はちびちび食べて、食べ終わりました。この日までは味もかわらず美味しく頂けました。
■スモークサーモンのデータ
手法
ソミュール法
参考:お刺身用〆サーモン
参考レシピ
2012年末作成
2013年末作成
(乾塩法)
サーモン
3kg
チリ産 大きめで脂のりのり
1匹約1.8キロ。
7.7kg 半身10枚
ノルウェー産 やや小ぶり。脂はチリ産よりは少なめ。
1匹約1.2キロ。
9.1kg 半身16枚
1kg
塩
1kg
(水の20%)
500g
(水の10%)
1.2kg
(水の12%)
40g
(鮭の4%)
砂糖
300g
(水の6%)
150g
(水の3%)
300g
(水の3%)
(もう少し多くてもいいか?)
20g
(鮭の2%)
その他・スパイス
ソミュール液用 黒粒胡椒
オイル漬け用に太白胡麻油
ソミュール液用にローレル、黒胡椒粒、タイム
ソミュール液用にローレル、黒胡椒粒
オイル漬け用に太白胡麻油
胡椒、ローリエ、ディルなど適宜
水
5リットル
5リットル
10リットル
----
乾塩法の塩分濃度
(*1)
----
----
----
(40+20)/1000
=6%
ソミュール法の塩分糖分濃度
(*2)
(1000+300)/
(5000+1000+300)
=20%
(500+150)/(5000+500+150)
=11%
(1.2+0.3)/(10+1.2+0.3)
=13%
----
下ごしらえ
(*3)
ピチット5時間
↓
塩漬け10時間
↓
(塩抜きなし)
↓
乾燥9-10時間
↓
オイル漬け10時間
↓
乾燥10時間
塩漬け15時間
↓
ゆすぎ洗い
↓
(塩抜きなし)
↓
ピチット20時間くらい
塩漬け16時間
↓
ゆすぎ洗い
↓
塩抜き1時間弱
↓
ピチット24時間
↓
(一部のみオイル漬け約10時間)
↓
(オイル漬けしたものは再度ピチット一晩)
塩漬け12時間
↓
ゆすぎ洗い
↓
(塩抜きなし)
↓
食べる
(ゆすいだ後ピチットや昆布などで脱水しても可)
燻製
15-30度
1日あたり10時間程度を5日間
(温度は初日ほど低め。最終日は温度高めで5-6時間)
初日雨だったためスモークののりが悪く、3日ほどかけて燻製。
燻製後、吊して干したりした。
30度以下
1日あたり数時間を2日程度。
最初は煙を流しながら。
初日は鮭を網に水平にのせた。
2日目はヒモをつかってぶら下げてスモーク。こうするとスモーカー1台で12匹つるせる。
----
レシピに関する補足
ホテルのレシピ。
砂糖は果糖を使用。
鮭:ソミュール液
=1kg:1.7リットル
鮭:ソミュール液の水の量
=1kg:0.6リットル
(これでは足りない)
鮭:ソミュール液の水の量=1kg:1.1リットル
塩漬け12時間後、塩分がまだ溶け残っていることもあった
出典
『燻製工房』 (平凡社)
fleur de sel さんのレシピで
2007年1月に初挑戦
10%のソミュール液はあれ?というくらい薄く感じた。
ソミュール液の量が圧倒的に足りず、鮭が密着して味がよく染みておらずよくなかった。干すことで、なんとか塩分濃度があがっていった。
ソミュール液は10リットルで十分足りた(鮭より多い水の量だとよさそう)。
12%のソミュール液は、かなり塩辛い。(煮溶かしたあと、蒸発した可能性もある)
鮭は途中塩辛いかと思ったが食べると丁度いいくらい。
甘さはあと少しあってもよかったか。
オイル漬けすると身が痩せにくいような気がした。味は同じか、やや塩味マイルドに感じるかもしれない。
(*1)乾塩法の塩分濃度: (砂糖+塩)/鮭 計算結果は小数点以下斬り捨て
(*2)ソミュール法の塩分濃度: (塩+砂糖)/(水+塩+砂糖) 計算結果は小数点以下斬り捨て
(*3)ゆすぎ洗いの後はキッチンペーパーなどで拭き取る